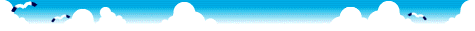|
谺俳句 |
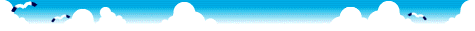
 |
主宰作品(1月) |
|
|
 |
秀嶺集 ① (1月) |
|
|
 |
秀嶺集 ② (1月) |
|
|
 |
山巓集(1月号) |
|
|
 |
谺集(抄) (1月号) |
|
|
 |
主宰作品(12月) |
|
|
 |
秀嶺集 ① (12月号) |
|
|
 |
秀嶺集 ② (12月号) |
|
|
 |
山巓集(12月号) |
|
|
 |
谺集(抄) (12月) |
|
|
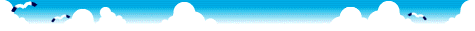
 |
谺俳句 |
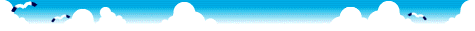
 |
主宰作品(1月) |
|
|
 |
秀嶺集 ① (1月) |
|
|
 |
秀嶺集 ② (1月) |
|
|
 |
山巓集(1月号) |
|
|
 |
谺集(抄) (1月号) |
|
|
 |
主宰作品(12月) |
|
|
 |
秀嶺集 ① (12月号) |
|
|
 |
秀嶺集 ② (12月号) |
|
|
 |
山巓集(12月号) |
|
|
 |
谺集(抄) (12月) |
|
|